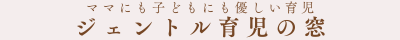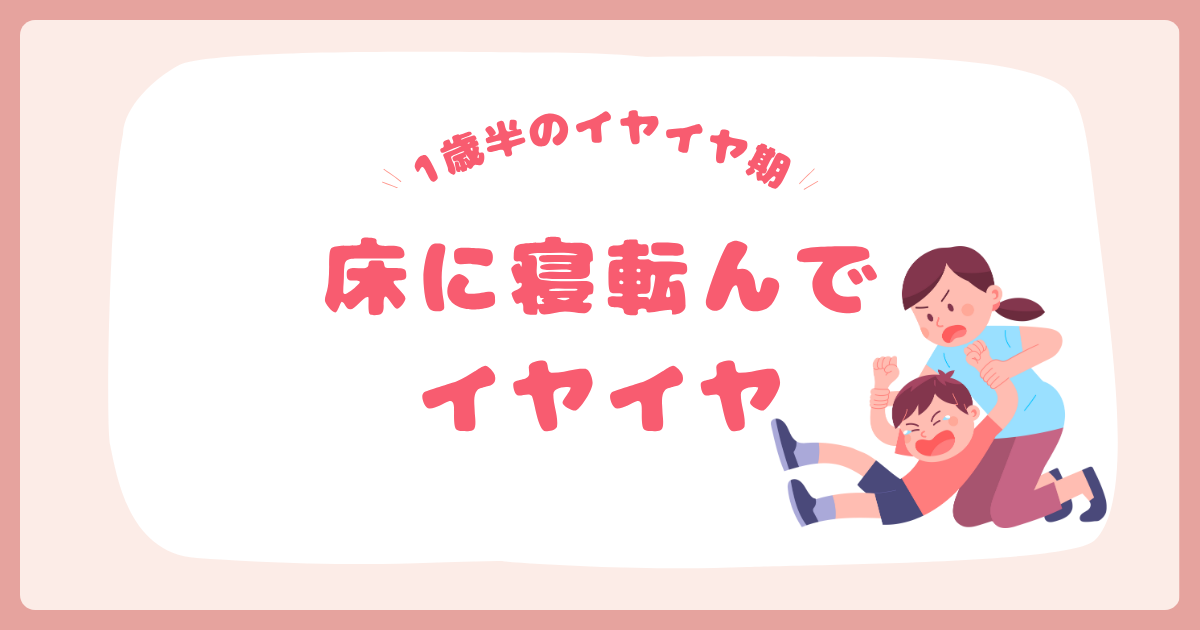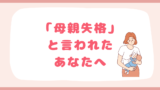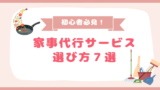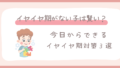こんなところで床に寝転がらないで〜〜〜
周りの視線が痛いよ〜〜〜
- 突然、嫌なことがあったのか床に寝転んで「いや!!」と叫んでいる
- 大泣きで周りの目が痛い‥
- 無理やり抱えようと思っても、どこからこんな力が出てくるの!と困惑
- 怒鳴ってしまって、余計に悪化して大惨事‥後から反省
こんな経験をお持ちの方もいますよね。
こんな経験が続くと、外出するのが億劫になってしまったり、憂鬱になってしまうこともあるかもしれません。
しかし、子供と一切出掛けないことは難しいのが現状ですよね。
今回の記事では、今回は、1歳半を過ぎたイヤイヤ期真っ只中の娘を育てている育児法収集マニアの筆者の実体験と、海外の育児法「ジェントルペアレンティング」に基づいて
叱らないで床に寝転ぶイヤイヤ行動の適切な対応3ステップ
をご紹介します。
これを実践するには「親のメンタル・心構え」がとっても重要です‥
でも遠回りなようで、近道な方法かなと思います。
子育てママみんな頑張ってます!一緒に乗り越えましょう!
ぜひ最後まで記事をご覧いただけますと幸いです。
床寝転びに対する事前準備:親の心構え
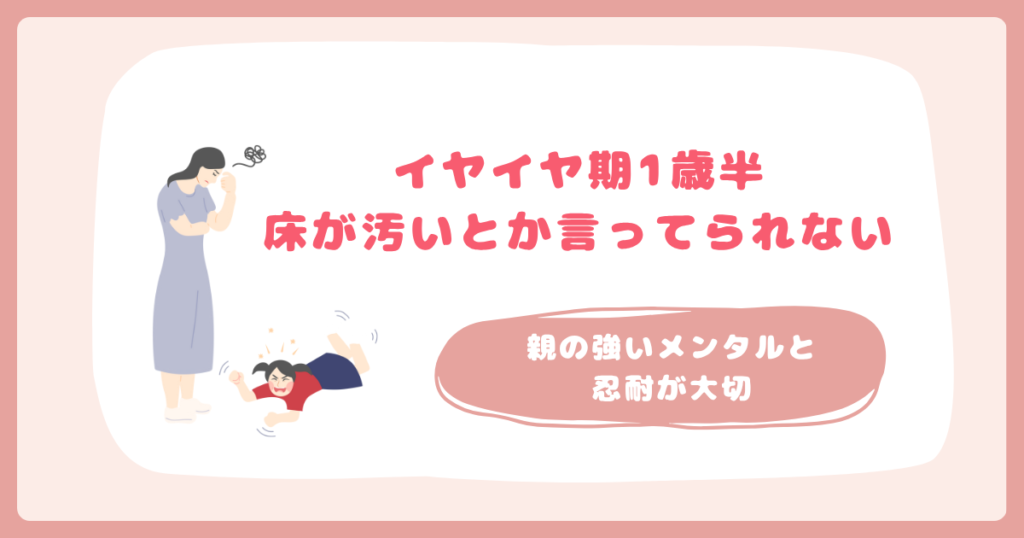
子どもが床に寝転んでイヤイヤしている姿を見ると、親のメンタルがやられますよね。
まずは、親の成長と思い、心構えについて解説していきます。
床が汚い・衛生面については一旦考えない
子供が床に寝転んだ時に、真っ先に思い浮かぶ感情が
「汚い!!!」
という方もいるのではないでしょうか?
確かに衛生的にも心理的にも嫌ですよね。

うちの子も、公園の公共トイレの床(和式便所とかも近くにある床)に座った時は、流石に心が砕けました‥
しかし、小さいうちは「菌」に触れた方が、獲得免疫が増えるという説もありますよね。
本当かどうかは一旦置いておいて、床に寝転んでも「菌を獲得しているんだ‥」と自分に言い聞かせて、一旦「床が汚い」という感情は捨てましょう。
周りの目が気になる
床に寝転んで泣いている我が子を見る周りの視線が冷たくて辛い‥
これは結構しんどいですよね。
しかし、周りの人から何を思われていたとしても、自分には関係のない話です。
きっとその場では何か思われたかもしれませんが、5分後にはきっとその人たちは忘れてしまっているでしょう。
そんな気持ちで、周りの目は一旦無視して我が子を落ち着かせることに集中しましょう。
周りの目を気にしないための方法について詳しくはこちらの記事でも解説しています。
床に寝転んでイヤイヤした時の対処法 3ステップ
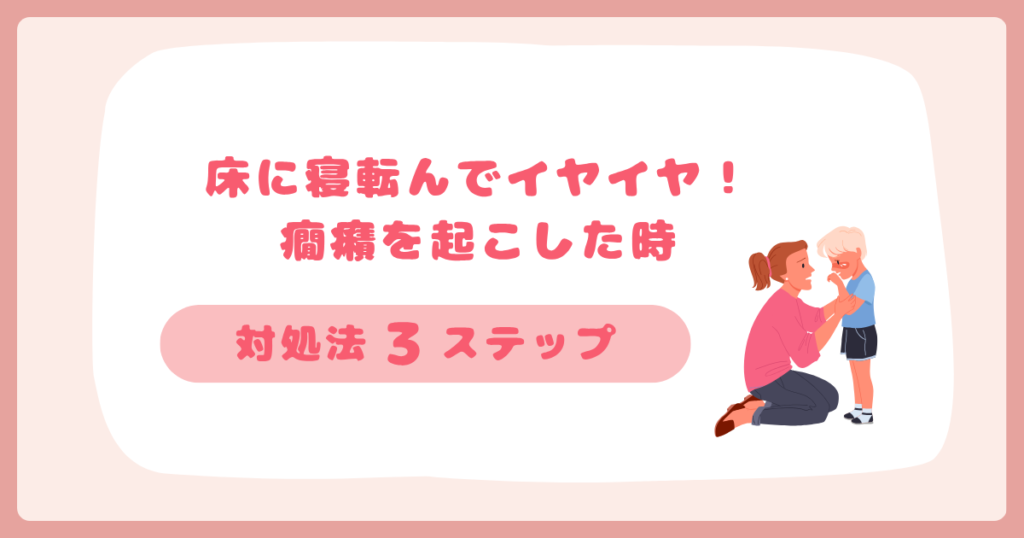
1:共感と理解の声かけ
さっきまでご機嫌で過ごしていたのに、突然嵐が来たように泣き出して床に寝転んでしまう‥
こんな時、子供が癇癪を起こすきっかけは必ずあります。
私たち親はそのタイミングを親は見逃さないようにしましょう。
- 「嫌だったね」
- 「もうやりたくなかったんだね」
- 「触りたかったんだよね。」
- 「まだ遊びたいんだね。」
など、子どもの感情をそのまま受け止める言葉をかけることで、子どもは「理解してもらえた」と感じ、少しずつ落ち着きを取り戻します。
2:感情のラベル付けを助ける
子どもが癇癪を起こして泣き出した時に
- 「怒っているんだね」
- 「できなくて悔しかったね。」
- 「理解してもらえなくて悲しかったよね。」
などと感情の名前を教えてあげると、子どもはその感情を自分で言葉にできるようになります。
これにより、徐々に寝転ぶ以外の方法で感情を表現することができるようになります。
3:気持ちの切り替えを手伝う
共感の声かけなどをしてあげると子供が早めに冷静になって落ち着きを取り戻すケースもありますが、一方で、一度癇癪を起こしたら親の話など一切聞こえない・耳を貸さないと言うケースもあります。
これは子供の気質によって違うので、もし聞き入れてもらえないようだったら、一旦落ち着くのを待ってから、1・2で挙げたような声かけをしてあげるのが良いと思います。
その場合は、周りが安全であるかを確かめてから。
少し落ち着きを取り戻して話を聞き入れてくれそうになったら、気持ちの切り替えを手伝ってあげましょう。
- 「こっちにもおもちゃがあるよ!」
- 「車に戻ったらおやつを食べようか」
気持ちが切り替わると「ケロっ」とすることもあります!
子供が床に寝転んでしまうことに悩んでいる人に伝えたいこと
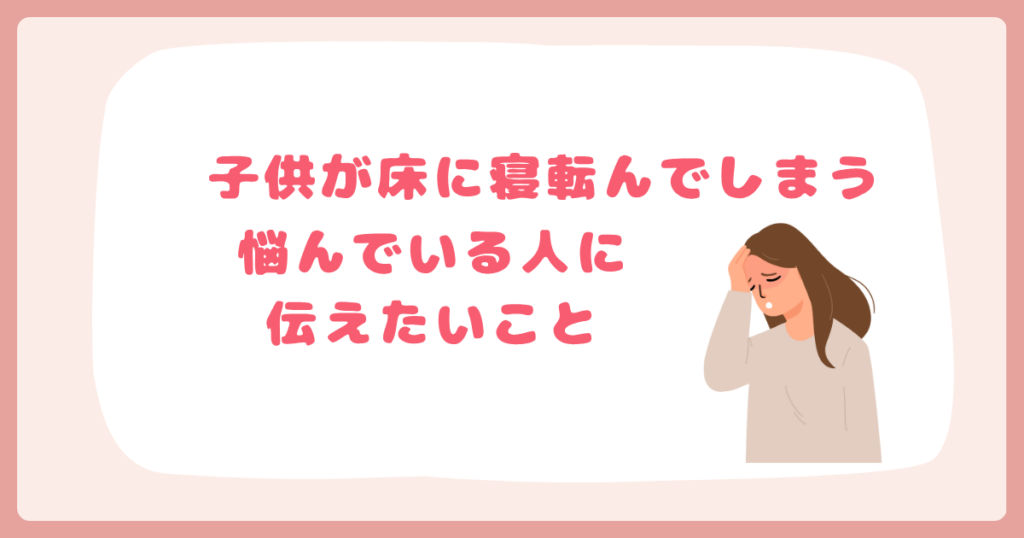
寝転ばない子が羨ましい・・・違いって何?
イヤイヤ!と感情表現をしつつも、床には寝転ばない子もいますよね。
- 「なんであの子は寝転ばないの?」
- 「私の育て方が悪いのかな…」
- 「うちの子だけ扱いにくい?」
と不安になってしまうことありませんか?
でも、実は “寝転ぶ子/寝転ばない子の違いは、性格の優劣ではありません。”
そして、ママの育て方とも関係ありませんよ。
✔ 違いは「気質」と「経験」による“表現の仕方”だけ
子どもはそれぞれ、生まれつきの気質で、気持ちを「外に出すか」「内にためるか」 のスタイルが違うんです。
寝転ばない子は、「イヤな気持ちを感じていない」のではなく、内側で処理したり、別の方法で伝えているだけ。
大人でも、すぐに泣いてスッキリする人と、黙って耐える人がいるのと同じです。
✔ 寝転ばない=我慢できている、というわけではない
一見、落ち着いて見える子でも、実は胸の中で グッと我慢しているだけ ということがあります。
- 我慢が得意
- 慎重で周りをよく見る性格
- “この方法は効かない”と過去の経験で学んでいる
こんな背景があるから「寝転ばない」だけで、決して“良い子”だからではありません。
それに、普段は寝転ばない子でも、家では激しく泣く“内弁慶タイプ”もいます。
ママが見ていないところで我慢しすぎていたら、むしろケアが必要になることすらあります。
✔ 寝転ぶ子は「感情表現が豊か」なだけ
一方で、寝転ぶ子は、
- 気持ちを外に発散しやすい
- 安心できる人の前だと全出しできる
- 感情を身体で表現するタイプ
という “豊かな表現スタイル”を持っている子です。
これは全く悪いことではありません。
むしろ、自分の感情に気づいて外に出せる=自己主張ができる子でもあります。
自分の意思を思いっきり出せるのは、「ママの前だから安心して出せている証拠」 です。
大きくなるにつれて、言葉で説明したり気持ちを整理する力が育ってくると、自然と落ち着いてくる行動なので、安心して見守りましょうね。
親が無理をしないのが一番大切
毎日の理不尽なイヤイヤ主張は、本当に精神が参ってしまいますよね。
これがいつまで続くんだろう・・・?
そんな不安に駆られた人もいるのではないでしょうか?
毎日が不安でストレスに感じている人は、子供を思い切って預けたりして、少しリフレッシュするのは本当に大切です。
こんなにイヤイヤ期で顔も見たくなかったのに、ちょっと離れたら早く迎えにいきたい!と思ってしまうものだから不思議ですよね。
- なんだか自分の顔が疲れている気がする
- 笑顔が減ったかも
- 最近大人と話してないのでは?
- ストレスで体にガタがきている
当てはまる人は危険信号。
罪悪感を抱かずに、親や旦那さん、保育園の一時預かりやベビーシッターなどに預けて自分の時間を設けましょう。
ベビーシッターは利用代金の一部を国が補助する制度があるのをご存知ですか?
この制度を利用すると、実質交通費の負担程度で、ベビーシッターを利用することができるんです。
通称『ベビーシッター補助券』で、これは企業が国に申請をする必要があり、個人で申請ができません。企業が申請後に従業員にベビーシッター券を福利厚生などの名目で配布します。
一度、ご自身や旦那さんの会社の福利厚生で、ベビーシッターの助成がないか調べてみるのも良いかもしれません。
ベビーシッター補助券の概要や、会社への相談の仕方などはこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ:辛いのは今だけ!親子でイヤイヤ期を前向きに乗り切ろう

今回は、イヤイヤ期の癇癪・床に寝転んでイヤイヤしてしまう子供への対処法と親の心構えについてお話ししました。
イヤイヤ期や、こういった癇癪で床に寝転ぶと言う行動には必ず終わりが来る。
そんな言葉をいろんなところで聞いているので、きっとそうなのだと思います(まだイヤイヤ期の最中)
大人になっても、床に寝転んでる人っていませんもんね‥?きっと終わりが来るのでしょう。
こうやって対策法などを検索されているママたちは本当に勉強熱心で頑張っていると思います!
一緒に育児、乗り切りましょうね。
改めて伝えますが、親自身が「しんどい」そんな気持ちになっていたとしたら‥
一度他の人の手を借りてみるのもおすすめ。
私もベビーシッターや家事代行、保育園の一時預かりを利用し出して、かなり心に余裕が生まれました。
家事代行にはベビーシッターも兼任している人もいます!
比較記事はこちらから
最後までご覧いただきありがとうございました。