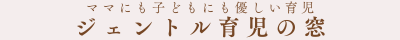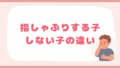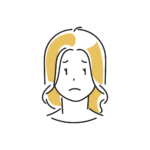
一人で歩けるようになった途端、道路に飛び出してしまいそうでヒヤヒヤする‥
子供にどうやって危険を教えていったらいいの?
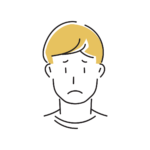
道路に飛び出すから「だめ!」って言ったら癇癪を起こして大変なことに‥
安全教育っていつから始めたらいいの?
こんな悩みを抱えている人のための記事です。
この記事では、子供の安全教育の5つのステップについてご紹介していきます。
子供は年齢によって理解度が変わってくるので、年齢別の安全教育についても解説しています。

「叱る」という手段だけではない安全教育の方法もあるので、今回はそれを重点的に解説していきますね。
もちろん本当に危ない時には大きな声で子供に危険を知らせることも大切です。
子供に対して、叱ったり、大声を出してしまう自分に自己嫌悪になってしまうような方は必見です。
安全教育の大前提:なぜ子供は飛び出してしまう?
子供の安全教育は年齢によってフェーズが違います。
歩けるようになったばかりの1歳半〜2歳ごろの子供には「車が危ない」という感覚がないので、興味のある方に向かっていってしまうのです。
それがイヤイヤ期に被ってしまうと、車がきていて危ないから行動を止めたら、やりたいことを妨害されたことで癇癪を起こすなんてことも‥
しっかり親の言うことが理解できる年齢になった小学生以降でも、子供の急な道路の飛び出しはあります。
子供は一点に集中しやすいので、「ボールを追いかける」「友達と遊ぶ」など、目の前のことに夢中になると周囲の危険に気づかず飛び出してしまうことも。
また、「車の速さ」を正確に判断する能力が未発達な場合は、車との距離だけを基準に「まだ渡れる」と自信を持ってしまってヒヤッとする場面に出くわすこともあるでしょう。
この記事は、イヤイヤ期の子供の安全教育をメインに5ステップでご紹介していきますが、小学生以降の部分については、後半の年齢別の部分で説明することにします。
子供への安全教育5つのステップ
では、イヤイヤ期の子供へ安全教育を行うための5つのステップについて解説していきます。

1. 事前に予防策を教える
まず、子どもと一緒に道路に出る前に、基本的なルールを教えておきましょう。
「道路は車が通るから危ないよ」
「お母さんやお父さんと一緒に手をつないで歩こうね」
などと、子どもに理解しやすい言葉で、危険性と必要な行動について伝えます。
危険な行動をとった後に注意してやめさせると、子供は「やりたいことを邪魔された!」と勘違いするかもしれません。
ポイントは「事前に」です。
最初に伝えておくというのは、忘れがちではないでしょうか?
道路に出る前に最初に伝えるというのを意識してみると良いかもしれません。
2. 親が模範行動を示す
大人が普段の行動で安全意識を示すことも効果的です。
信号が青になっても確認する、手をつないで渡るなど、子どもが見習いやすい行動を見せましょう。
私も、信号が赤に変わってしまいそうになったら、周囲を確認せず渡ることもあるので、子供からしたら道路に走って飛び出しているようにも見えてしまっているかもしれないですよね。
横断歩道を渡る、信号を守る、信号が青になっても車が止まってから渡るなど、子供に期待する行動をまずは親が実践することで子供は親の行動から学ぶことができます。
3. 共感を持ちながら「なぜ危険か」を教える
「走って行きたい気持ちわかるよ」と共感しつつ、「でも、車が来ると大変なことになるよ」と危険性についても丁寧に伝えます。
頭ごなしに、「危ないじゃない!」「急に走らないで!」など伝えても、子供は理解ができていない場合もあります。
子どもの気持ちに寄り添いながら説明することで、子どもも話を理解しやすくなります。
「これをしちゃダメ!」と言うだけではなく「ママと手を繋いでいたら自分で歩いていいよ」などとポジティブな選択肢を与えてあげることで、気持ちが落ち着く子供もいるでしょう。
子供に危険性を教育するときは、危険な状況を回避した後は、子供を落ち着かせてからしっかり話すことが大切になるので、落ち着かせる手段として「共感」や「他の選択肢」という声かけを利用して子供と対話することも必要になってきます。
4. 短いフレーズで繰り返し伝える
- 「道路は危ないよ」
- 「車がくるよ」
といった短くて分かりやすい言葉を繰り返し伝えることで、子どもが自然と身につけやすくなります。
危険な場面だけではなく、日頃から繰り返し伝えることが大切です。
5. 成功を褒めて自信を持たせる
子どもが安全に道路を渡れたときには、「一緒に手をつないで渡れてよかったね!」と褒めてあげましょう。
安全な行動を取るたびに褒めることで、子どもは安心して従いやすくなり、自信もつきます。
道路に飛び出す行為は、好奇心旺盛な子どもにはありがちな行動ですが、根気よく教え、安全意識を徐々に身につけさせていく姿勢が大切です。

年齢別の対応方法についてもご紹介!
先ほど説明したアプローチは、おおよそ2歳ごろから対応可能です。
2歳頃になると、子どもは言葉を理解し、親が伝える基本的なルールを少しずつ覚えるようになります。
また、親がすることをよく観察してまねをしようとする時期でもあるため、大人の行動を見せることが効果的です。
しかし、年齢や発達段階によって理解度や対応の仕方も異なりますよね。
ここからは年齢別の安全教育について解説していきます。
1歳の安全教育
基本的な安全の習慣を作る段階です。
この年齢では理解が難しいこともあるため、道路に出るときは常に手をつなぐ、目を離さないなど親が積極的に安全を守ります。
短い言葉で「動いてる車は、怖いよ」など簡単なフレーズを繰り返して伝えます。
この時期はまだイヤイヤ期などもない子供も多いので、親が模範行動を見せながら、安全な行動を言葉で説明していくことで、安全な行動をとる基礎を作っていく時期です。
1歳半をすぎてくると、イヤイヤ期も始まってくるので、そうなったら先ほど述べたアプローチを根気強く続けていくと良いでしょう。
2歳の安全教育
少しずつルールが理解できるようになり、好奇心も旺盛になる時期です。
イヤイヤ期も真っ盛りという感じでしょうか。
この時期は先ほど述べたアプローチが有効です。
親が手本を見せながら「ブーブーが走る道路は危ないよ」と繰り返し伝えると効果が出やすくなります。
また、子ども自身が守れたことを褒めるなど、少しずつ自立心も育てられるようなアプローチも加えていきます。
3歳〜4歳の安全教育
簡単な約束やルールを理解しやすくなり、自分で行動する力も育ちます。
「手をつないで歩こうね」といった指示が伝わりやすく、注意を促すことで少しずつ安全意識を持たせることができます。
親が模範行動をしていくことで、子供も同様の行動をすることができるようになってきます。
各年齢に応じたペースで、子どもの理解度を見ながら進めていくことがジェントルペアレンティングの基本です。
5歳以降の安全教育
基本的な安全ルールを理解していても、判断を間違えてしまうことや、他のことに集中していて忘れてしまうことがあるのが、このくらいの年頃。
子供の判断能力の未熟さを大人が理解し、「車が見えたら渡らない」「車が止まるのを見届けるまで渡らない」など、シンプルで確実なルールを繰り返し教えることが重要です。
遊んでいる最中や下校中など、子供が集中しているときや興奮しているときほど飛び出しやすいと言うことを事前に伝え、注意喚起を行いましょう。
このくらいの年齢になると、理解力も高まるので、実際の道路で「どのタイミングなら渡れるか」を親子で体験し、子供自身に自分の判断の不確かさを気づかせる実験などをするのも良いでしょう。
(その場合は、親がしっかり安全を確保して行なってくださいね。)

まとめ
道路に飛び出ししまう行動は、好奇心旺盛な子供に見られる行動ですが、これも成長発達の一環です。
子供を危険な目に合わせる前に、事前に説明をして理解をさせるということが大切です。
最初は、理解してくれない・言っても聞かないなどの悩みがあると思いますが、焦らず根気よく教えることで、安全意識を育てることができます。
家事に育児に忙しいと、なかなか理想の子育て・教育ができないことも多いですが、今日の記事を見て1つでも参考になることがあれば嬉しいです。
ママさんの育児の負担が少しでも軽くなることを祈っています。