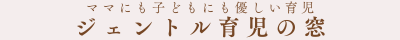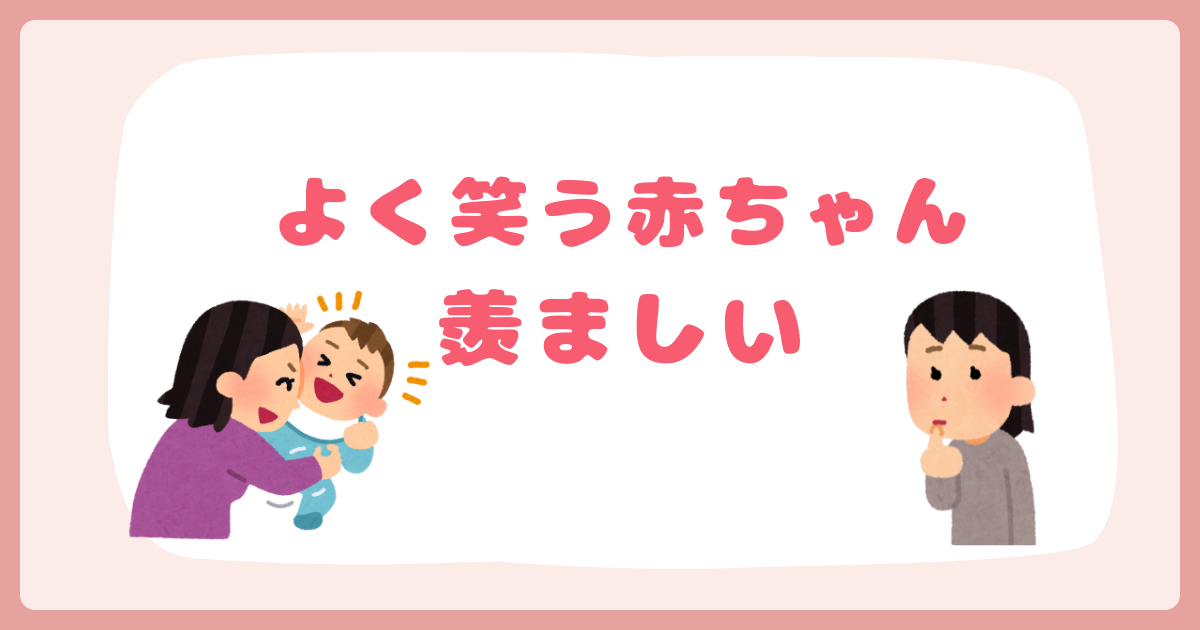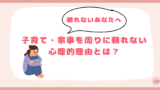うち子は、他の赤ちゃんより笑顔が少ない気がする‥
周りの子がニコニコしている姿を見ると『自分の子どもはしっかり成長しているのか?』『何か発達の問題で笑顔が少ないのではないか?』と不安になりますよね。
しかし、その不安な気持ちは、子どもを大切に思っている証拠です。
赤ちゃんの笑顔は、個性や成長スピードで大きく変わってきます。
親の責任や育て方の問題ではないですよ。
今回は、「他の子どもや赤ちゃんと比べてしまう」心理を知って、自己理解を深めましょう。
そして、赤ちゃんだけではなくて、親のあなたも笑顔になるきっかけの記事になるといいなと思います。
自分が笑顔でなければ、赤ちゃんだけ笑顔になるのは難しいかもしれませんよ。
この記事を読んでママの心の負担が少しでも軽くなれば幸いです。
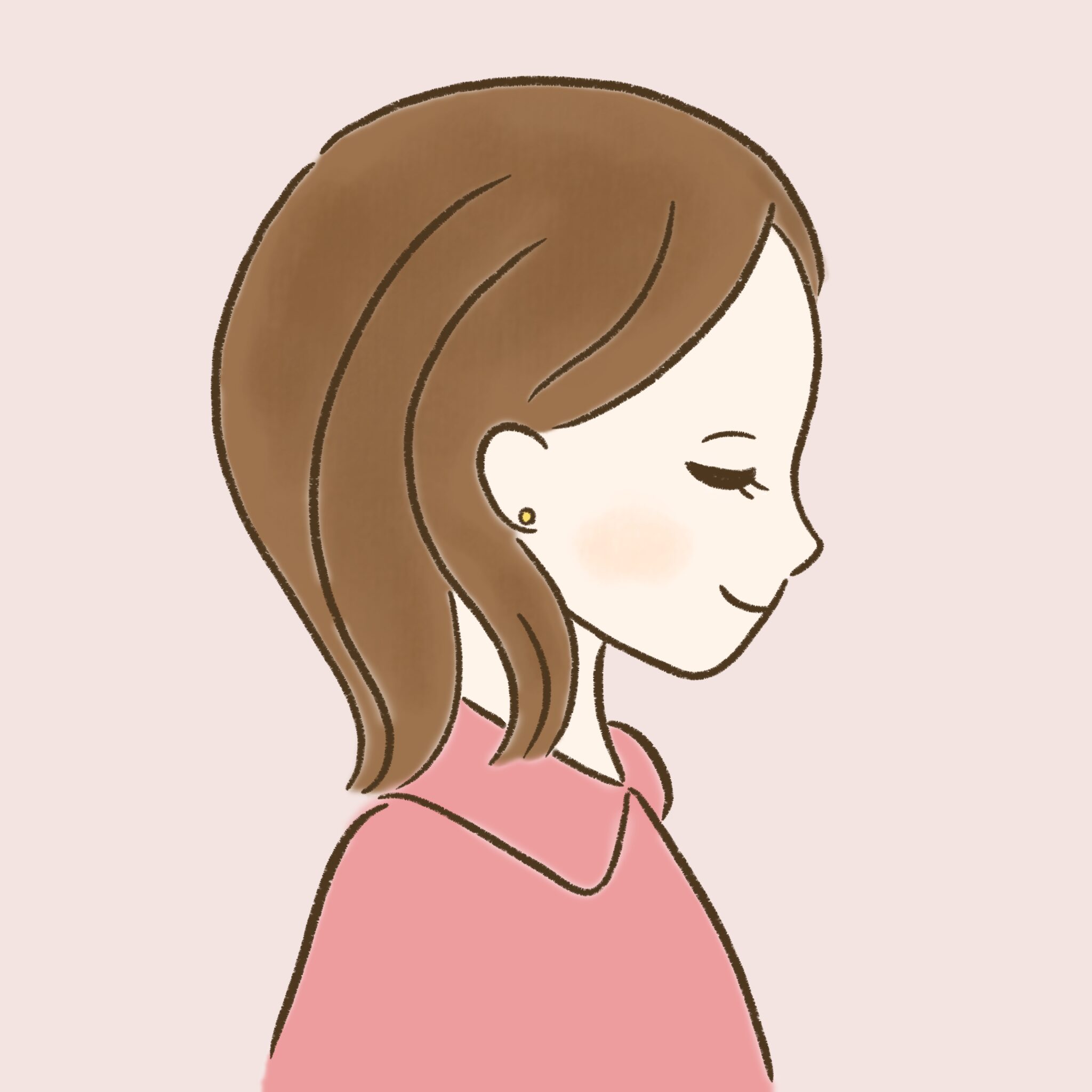
2歳の娘がいるセナママと申します。
私は、産前うつを経験していて、そこから子育てに関して書籍を読んだり調べたりするのが日課になっている育児オタクです(笑)
鬱になった経験から、心理学についても独学で勉強中📖
海外のジェントルペアレンティングという育児を元に、いろんな教育法を取り入れながら子供と向き合う日々を送っています。
笑顔な赤ちゃんを羨ましいと思ってしまう心理とは?
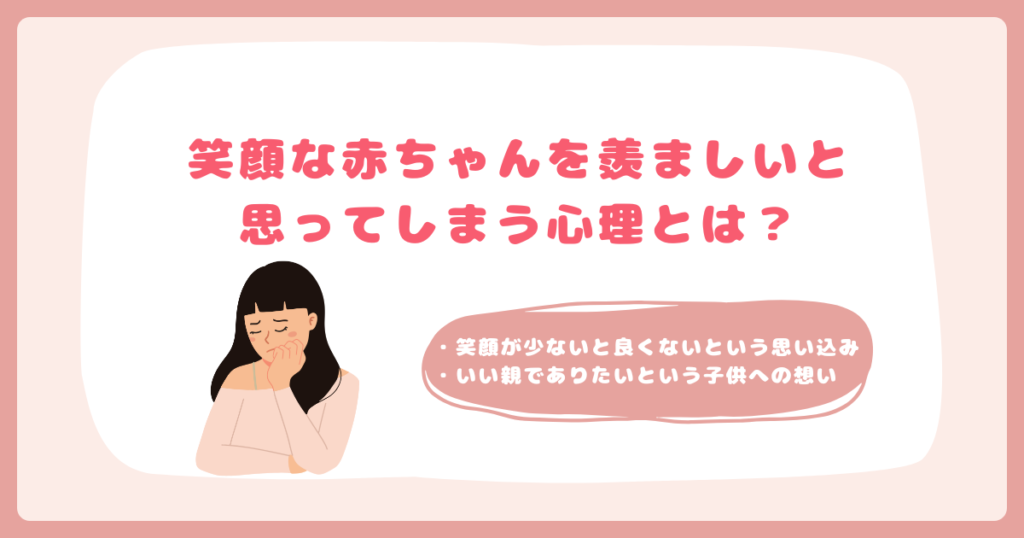
笑顔が少ないと良くないという思い込み
赤ちゃんの笑顔について検索すると、こういった関連検索キーワードが出てきます。
- 笑顔が少ない 親の愛情不足
- 笑顔が多い子は賢い(=うちの子は賢くない?)
- よく笑う赤ちゃん 幸せ(=笑わないのは幸せを感じていない?)
こういった情報が検索関連で出てきてしまうと、不安は募りますよね。
しかし、これは科学的根拠は全くありません。
テレビ・ネット・SNSなどでは「専門的に正しい情報」よりも「不安を刺激する言葉」の方が注目されやすい傾向があります。
そういった傾向から、笑顔が少ないことが良くないという誤った知識の広がりにつながってしまっていると言えます。
いい親でありたいという子供への想いの裏返し
自分の子どもにとっていい親でありたいという気持ちから、他人の子どもと自分の子どもを比較して、不安な点・改善点を無意識のうちに探してしまっている可能性があります。
笑顔な赤ちゃんを羨ましいと感じて検索をしている時点で「あなたは子供に向き合っている素晴らしい親」だと私は思っています。
うつを経験した私だから、言えることは「自分を責めすぎない・追い詰めすぎない」ことが大切ですよ。
我が子はなぜ笑顔が少ないの?
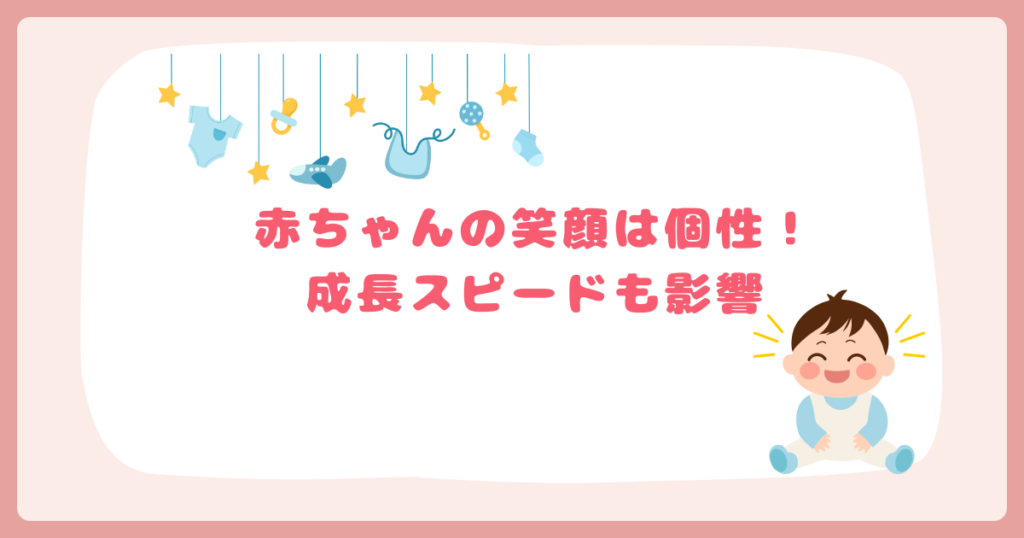
赤ちゃんがよく笑う理由:生まれつきの性格!
赤ちゃんによって、生まれもった性格・気質によって笑顔の頻度は大きく違います。
生まれつきよく笑う赤ちゃんも、もちろんいます。
しかし、控えめな性格の赤ちゃんは感情を表に出しづらく、笑顔が少ない・表情が少ない子もいます。
これは個性であり、生まれつきの性格なので、親の育て方・環境が要因ではありません。
| 項目 | よく笑う赤ちゃん | 笑いが少ない赤ちゃん |
|---|---|---|
| 気質のタイプ | 感情表現が豊かで社交的な傾向 | 観察力が高く、慎重な傾向 |
| 笑顔の多さ | 表情で気持ちを伝えるのが得意 | 笑顔以外の方法で気持ちを表す(まばたき・体の動きなど) |
| 外からの刺激 | 笑って反応することが多い | じっと見つめて情報を吸収する |
| 安心する環境 | 賑やかでも楽しめる | 静かで落ち着いた環境を好む場合がある |
| 人見知り | あまり見られないことも | 慎重に相手を観察してから心を開くタイプ |
| 親との関係 | 表情の反応があるため関わりやすく感じる | 一見反応が薄くても、しっかり親を見つめ信頼を育んでいる |
| 成長面の特徴 | 社交的な力が育ちやすい | 深く物事を考える集中力・観察力が育ちやすい |
成長につれて笑顔が増える!発達には個人差がある!
生後2〜3ヶ月ごろから「社会的微笑」という人の顔や声などの外的な刺激に反応して見せる笑顔が出始めます。しかし、これも発達に個人差があり、生後4〜5ヶ月から現れる子も。
また、性格によっては外部の刺激に対して繊細に反応してしまう子もいるので、一概に「笑顔」という反応を見せないケースもあります。
だんだん、外部の刺激に対して安心できるものであると認識できたら「笑顔」を見せてくれる機会も増えるはずなので、焦らずに見守ってあげることができたらいいですね。
笑顔を引き出すために、親ができることはある?
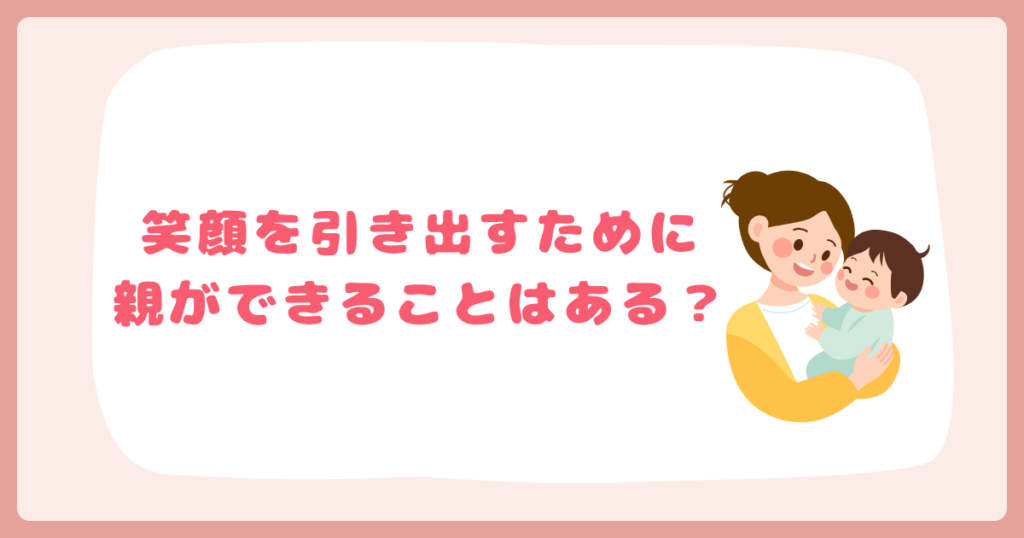
日々のスキンシップ
日々のスキンシップを図ることで、親子の信頼関係を構築したり、外部の刺激を赤ちゃんが肯定的に捉えられるようになります。
抱っこしたり、手をつないだり。肌と肌の触れ合いは、赤ちゃんにとってはもちろん、親にとっても、非常にリラックスできる瞬間になること間違いなし。
日々忙しく過ごしていると、スキンシップを取る時間が疎かになりがちなので、時間を決めて赤ちゃんと向き合う時間を取ることがおすすめです。
赤ちゃんに笑顔で話しかける
赤ちゃんに笑顔を向けることで、赤ちゃん自身もつられて笑顔を見せてくれることも。
笑顔で話しかけることで、親子のコミュニケーションが生まれます。「ありがとう」「大好き」などの愛を感じる声かけをすることで、子供の自己肯定感の向上にもつながりますよ。
スキンシップをとる時間に合わせて、赤ちゃんとお話しをする時間も一緒にとると、良いでしょう。
ママ・パパが笑顔の見本になる
大好きなママやパパが笑顔を見せてくれたら、赤ちゃんも自然とつられて笑顔になることも多いです。
今、鏡を見た時に「みなさんは笑顔でしたか?」
もし、今自分を客観視した時に、笑顔になれていないのであれば、赤ちゃんにもそれは伝わっているかもしれません。
まずは親が笑顔になれる瞬間を増やすこと目指してみましょう。
あなたの笑顔が少なくなっている理由はありますか?
- 元々、表情を作るのが苦手
- 子育てにいっぱいになりすぎて笑顔の余裕がなかった
- 大人と会話することが少なくなって、笑うことが減ってしまっている
様々な原因があるかもしれません。
一度、自分の笑顔が少なくなっている原因を突き止めましょう。
もし、子育てをスタートしてからの後天的な理由であれば、周りに頼って自分の負担を減らす努力をしましょう。
少し、頑張りすぎているのかもしれませんよ。ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
まとめ:親の笑顔が子どもの笑顔を引き出す

赤ちゃんの笑顔は、親子の絆やコミュニケーションを通じて育まれることを紹介していきました。
自分の子どもと他の子を比べてしまうのは、普通のことです。自分を責める必要はありません。
その中で、羨ましいと比べてしまって、どんどん気持ちが塞ぎ込んだり、笑顔が減っているようなら要注意。
一度、周りに頼って自分の心の余裕を取り戻しましょう。
赤ちゃんもママもパパも笑顔で過ごせる日々が増えることを祈っています。